第1節 脱炭素社会への移行に向けた世界の動向
1.国際的な各種枠組み・ルールの最新動向
世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加する等、気候変動問題への対応は今や人類共通の課題になっているといえます。前章に記載のとおり、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略等を受け、世界中でエネルギーセキュリティやエネルギーの安定供給に対する重要性が再認識されましたが、脱炭素社会の実現に向けた動きは引き続き加速しています。
(1)COPや金融面における動向
2022年11月にエジプトのシャルム・エル・シェイクで開催され、米国のバイデン大統領等、約100か国の首脳が参加した国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)では、前年のCOP26の方向性を踏襲しつつ、パリ協定の1.5℃目標1に基づく取組を実施していくことの重要性が再確認されました。他にも、1.5℃目標に整合的な温室効果ガス排出削減目標(NDC:Nationally Determined Contribution)を設定していない締結国に対して、目標の再検討・強化を求める等、脱炭素社会の実現に向けた国際的な取組の強化が見られました。
金融面では、カーボンニュートラルに貢献する投融資の枠組みに関する議論が進んでいます。官民双方での議論が活発化しているのは、トランジション・ファイナンスというファイナンス手法についてです。トランジション・ファイナンスとは、ファイナンス手法の1つで、脱炭素社会の実現に向けた長期的な戦略に則り、着実な温室効果ガスの排出削減の取組を行う企業の支援を目的としています。OECDは、2022年10月にトランジション・ファイナンスに関するガイダンスを公表し、パリ協定目標を達成する上でのトランジション・ファイナンスの重要性について言及しています。また、GFANZ2やNZBA3等のカーボンニュートラルを目指す民間主導のイニシアティブ動きも活発化しています。2022年6月にGFANZは、金融機関向けの、ネットゼロに向けたトランジション計画に関する提言とガイダンス4を公表しました。また、同年10月にはNZBAもトランジション・ファイナンスに関するガイダンス5を公表しています。
(2)カーボンプライシングを巡る動向
産業界における排出量取引制度や炭素税といったカーボンプライシングについても、様々な国・地域で制度設計や導入が進んでいます(第131-1-1)。制度内容の詳細は国や地域によって異なっていますが、一般的に排出量取引制度とは、政府が全体のCO2排出量の上限を設定し、ベンチマーク等に基づいて排出権(排出枠)を事業者に無償もしくは有償で配分、事業者はその排出権を市場で他の事業者と取引し、自らの実際のCO2排出量に相当する排出権を調達する義務を負う、というものです(実際の排出量が、保有する排出権より大きくなった場合は罰則が科される)(第131-1-2、第131-1-3)。また、一般的に炭素税とは、政府がCO2の排出に対して一定額の課税を行うもので、価格効果によるCO2排出の抑制を目的としています。
【第131-1-1】カーボンプライシングの導入国(2022年4月時点)
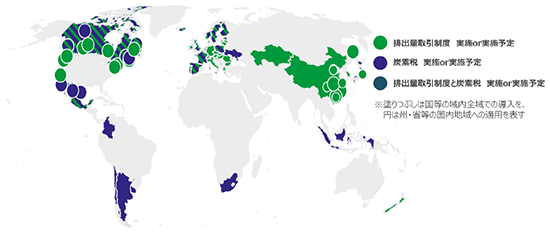
【第131-1-1】カーボンプライシングの導入国(2022年4月時点)(ppt/pptx形式:150KB)
- 資料:
- World Bank「Carbon Pricing Dashboard」を基に経済産業省作成
【第131-1-2】一般的な排出量取引制度のイメージ
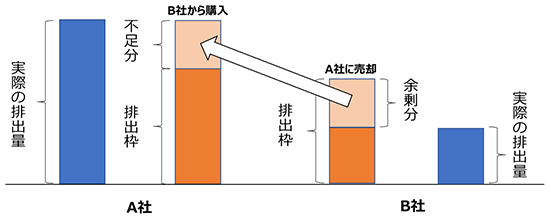
【第131-1-2】一般的な排出量取引制度のイメージ(ppt/pptx形式:42KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
【第131-1-3】排出量取引制度導入国の例
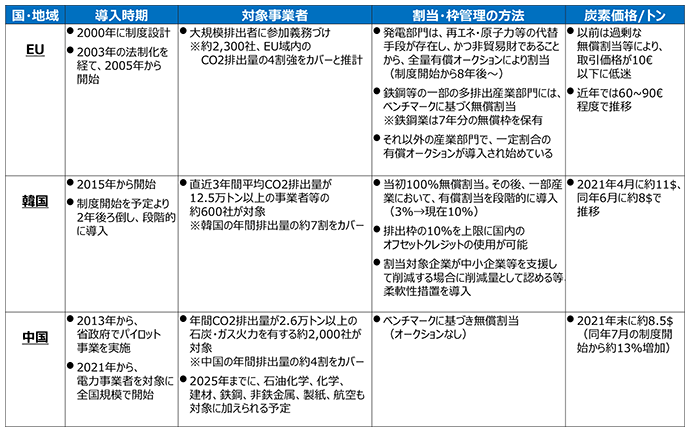
【第131-1-3】排出量取引制度導入国の例(ppt/pptx形式:46KB)
- 資料:
- 日本エネルギー経済研究所「排出量取引の制度設計の論点について(EU ETSの変遷と現状を踏まえて)」、各国政府公表資料を基に経済産業省作成
EUは、2021年4月に合意された欧州気候法において設定された2030年までの温室効果ガス削減目標(1990年比で55%以上削減)の達成に向け、2022年12月に、EUにおける排出量取引制度である「EU ETS」の改正指令案の暫定的政治合意を発表しています。段階的な排出量の削減と、毎年の排出量上限の削減率上昇により、排出量削減に向けた動きを加速させていく方針が示されています。またシンガポールでも、2022年には炭素税の引き上げの方針を公表しています。
世界銀行によると、こうしたカーボンプライシングの総額は年々増加を続けており、特に2021年はEU ETSを含む排出量取引制度の価格高騰に伴い、2020年の水準から60%近く増え、世界全体で約840億ドルとなっています(第131-1-4)。
【第131-1-4】カーボンプライシング収入の推移
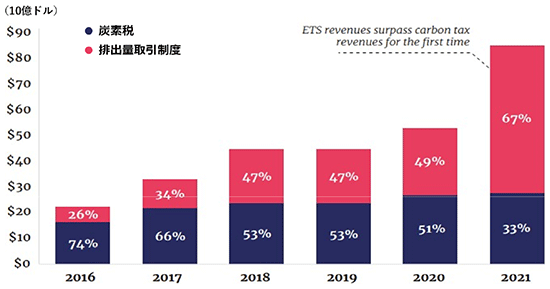
【第131-1-4】カーボンプライシング収入の推移(ppt/pptx形式:130KB)
- 資料:
- World Bank「State and Trends of Carbon Pricing」を基に経済産業省作成
このように、世界中でカーボンプライシングの導入が進む一方で、課題も残っています。例えば、排出量取引制度は、市場機能を活用することで効率的かつ効果的に排出削減を進められるという長所を有していますが、市場価格が変動することにより、カーボンプライスとしての予見可能性が低いことが課題として認識されています。カリフォルニア州やニュージーランドでは、排出量取引価格の上限・下限の設定や市場価格水準の設定を行うことで、カーボンプライスとしての予見可能性を高める動きも見られています。
また、こうしたカーボンプライシングの枠組みによって温室効果ガスの排出削減が強化される中、規制の厳しい地域から緩い地域への生産拠点の移転や、規制地域外からの輸入増加等が起こる、いわゆる「カーボンリーケージ」を問題視する声も高まっています。そうした中、EUは2022年12月に、炭素国境調整メカニズム(CBAM:Carbon Border Adjustment Mechanism)の設置に関する規則案について、暫定的な政治合意に達しました。カーボンリーケージの対策として、EU域内の事業者がCBAMの対象となる製品を域外から輸入する際に、域内で製造した場合に排出量取引制度に基づき課される炭素価格に対応した価格の支払いを義務づけるものです(第131-1-5)。また、韓国のようにカーボンリーケージのリスクがある産業に対し、排出枠を全量無償割当するといった対策を取っている国もあります。このように、様々な課題に対して各国の産業構造等を踏まえながら、カーボンプライシングの検討や導入が進んでいます。
【第131-1-5】CBAMのイメージ
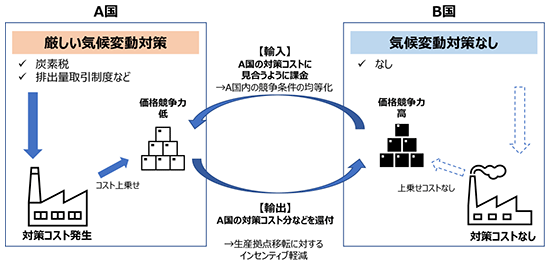
【第131-1-5】CBAMのイメージ(ppt/pptx形式:49KB)
- 資料:
- 経済産業省作成
2.脱炭素社会の実現に向けた各国の目標の動向
次に、脱炭素社会の実現に向けて各国が定めている目標について確認していきます。前述のとおり、国際社会は脱炭素社会の実現に向けて必要な枠組みやルールの策定を進めていますが、現在までに、2050年等の年限付きのカーボンニュートラルの実現を表明している国・地域は合計で150以上にものぼっており、これらの国・地域におけるGDPは世界全体のGDPの約94%を占めています(第131-2-1)。
【第131-2-1】年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域(2022年10月時点)
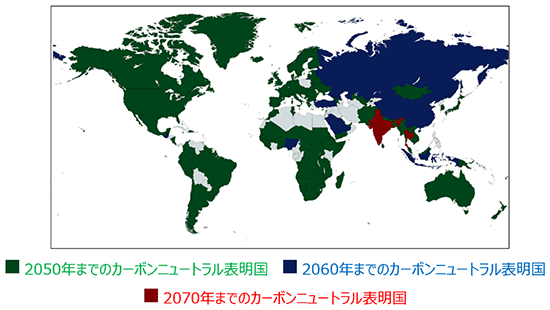
【第131-2-1】年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域(2022年10月時点)(ppt/pptx形式:299KB)
- 資料:
- World Bank databaseを基に経済産業省作成
また、こうしたカーボンニュートラル実現の表明に加えて、各国では2030年の温室効果ガスの削減目標を、NDCとして掲げています(第131-2-2)。2015年に採択されたパリ協定にて、全ての国にNDCを5年ごとに提出・更新する義務が設けられました。パリ協定で掲げた長期目標である「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃以内に抑える努力をする」を達成すべく、温室効果ガスの削減を加速化させる方向でNDCを更新する国もあります。
【第131-2-2】主要各国のNDC目標・カーボンニュートラル目標
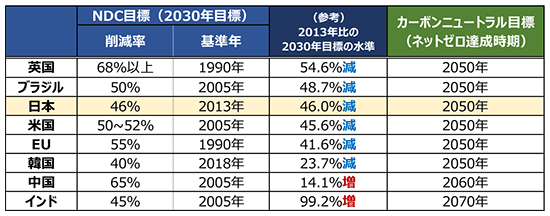
(注1)日本の基準年は2013「年度」、目標年は2030「年度」(カーボンニュートラル目標は2050「年」)
(注2)中国のNDC目標(65%)はGDP当たりのCO2排出量の削減率
(注3)インドのNDC目標(45%)はGDP当たりの温室効果ガス排出量の削減率
【第131-2-2】主要各国のNDC目標・カーボンニュートラル目標(ppt/pptx形式:46KB)
- 資料:
- RITE分析結果等を基に経済産業省作成
3.各国の政策
各国には、NDC目標を掲げたり、カーボンニュートラルの実現を表明したりするだけでなく、実際にこうした目標を達成していくための政策を立案、実行していくことも求められています。現在の産業構造や、エネルギー構成等は国によって大きく異なっているため、脱炭素社会の実現に向けた各国の政策は異なりますが、多くの国において、電化の推進や水素・アンモニアの活用、再エネの導入拡大、革新的イノベーションの実現等により、自らが掲げたNDC目標や、カーボンニュートラルの実現を目指しています。
特に2015年のパリ協定の採択以降、こうした脱炭素社会の実現に向けた各国の政策が加速していましたが、そうした中、2022年2月から始まったロシアによるウクライナ侵略は、こうした各国のエネルギー政策にも大きな影響を与えました。前章の第1節でも記載したとおり、これまでロシア産エネルギーへの依存度が高かった欧州諸国を中心に、ロシア産エネルギーの代替となるエネルギーを足元で確保する必要が生じたために、これまでのエネルギー政策の方向性からは一転、ドイツ等、石炭火力発電所の再稼働等の対応を取った国も現れました。
しかしその一方で、このロシアによるウクライナ侵略を1つの契機とし、国家を挙げて脱炭素に寄与する投資を支援する政策を発表する等、脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させている国も見られます。以下では、米国、EU、英国、ドイツ、フランス、インド、韓国等の国について、こうした脱炭素社会の実現に向けた政策動向を、ロシアによるウクライナ侵略前後の変化にも焦点を当てながら整理していきます(第131-3-1)。
【第131-3-1】カーボンニュートラルに向けた各国の政策の方向性
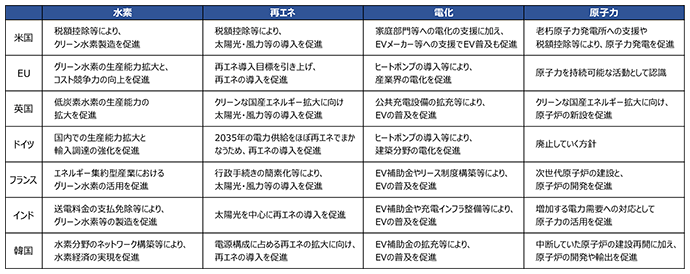
【第131-3-1】カーボンニュートラルに向けた各国の政策の方向性(ppt/pptx形式:47KB)
- 資料:
- 各国政府資料等より経済産業省作成
(1)米国
米国は、2030年までに温室効果ガスの排出量を2005年比で50〜52%削減し、2050年にカーボンニュートラルを実現することを目指しています。米国では、脱炭素社会の実現に向け、2022年8月には気候変動対策を盛り込んだインフレ削減法(Inflation Reduction Act)が成立しました。同法はカーボンニュートラルに向けた競争的な市場環境を促進しており、歳出予算案の85%を占める3,690億ドル(1ドル135円換算で約50兆円)を、エネルギーセキュリティと気候変動対策に対する投資に充てられることが決定されています。
インフレ削減法の中の気候変動対策として大きく掲げられているのは、太陽光・風力・地熱・バイオマス等の再エネや原子力発電といった、クリーン電力への移行を促進する方針です。再エネの導入を加速するために、再エネ関連の設備投資に対する投資税額控除や、生産税額控除等の施策がとられており、原子力発電に関しては、発電に応じた税額控除といった支援策がとられています。
クリーン電力同様に、水素やバイオ燃料等のクリーン燃料に対する税額控除も掲げられています。具体例として、クリーン水素への税額控除として、2032年までに建設を開始した施設を対象に、クリーン水素の生産量に応じて税額控除されます(その控除額は、ライフサイクルでの温室効果ガスの排出状況によって変動)。
電化を促進する方針も定められており、家庭部門や産業部門等に対する支援とともに、電気自動車(以下「EV」という。)メーカーに対する減税・補助の計画も含まれています。EVに関しては、2021年に成立したインフラ投資雇用法に基づき、2022年10月に米国エネルギー省がEV用バッテリーの国内生産拡大を目的としたプロジェクトに対して、合計28億ドルの助成金を付与することも発表しています。
米国は産業部門に特化した脱炭素化ロードマップ6も策定しています。2022年9月に、産業部門の脱炭素化に向けたロードマップがエネルギー省から発表されました。米国の産業部門における温室効果ガス排出量は、全体排出量の24%を占め、輸送部門(27%)、電力部門(25%)に次ぐ大きさとなっています。このロードマップでは、産業部門の脱炭素化における4つの柱として、①エネルギー効率の向上、②産業の電化、③低炭素燃料・原料・エネルギー源への移行、④CO2の回収利用・貯留(CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)を挙げており、2050年にはこれらの研究開発を強化することで産業部門の脱炭素を87%実現するとしています。また残りの13%についても、大気中のCO2を直接回収するDAC(Direct Air Capture)等の技術開発により削減することを目指しています(第131-3-2)。
【第131-3-2】米国の産業部門の脱炭素化に向けたロードマップ
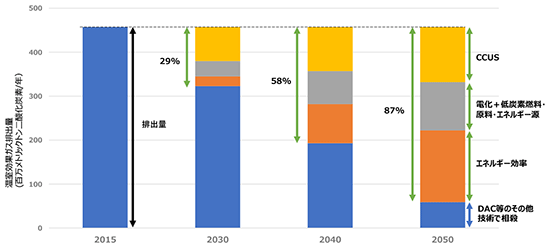
【第131-3-2】米国の産業部門の脱炭素化に向けたロードマップ(ppt/pptx形式:44KB)
- 資料:
- 米国エネルギー省「Industrial Decarbonization Roadmap」を基に経済産業省作成
こうした様々な政策の実行により、脱炭素社会の実現に向けた動きを加速している米国ですが、エネルギー省は現行の政策のみでは2030年のNDC目標(温室効果ガス排出量を2005年比で50〜52%削減)を達成できないと試算しています。インフレ削減法と2021年に成立したインフラ投資雇用法に掲げられた気候変動対策によって2030年までに削減できる温室効果ガス排出量は、2005年比で40%とされており、目標である50〜52%の削減を達成するには、追加の措置等が必要となっています。
(2)EU
EUは、2020年1月に「欧州グリーン・ディール投資計画7」を発表し、脱炭素社会の実現に向けて官民あわせて10年間で1兆ユーロ相当(1ユーロ136円換算で約140兆円)の投資の動員を目指しています。その後、EUは、2021年7月に「欧州気候法」を公布し、2050年のカーボンニュートラル実現と、2030年の温室効果ガス排出量を1990年比で55%以上削減することを法的拘束力のある目標として掲げています。そうした中、2021年にはこれらの目標の達成に向けた一連の政策パッケージ「Fit for 55」を発表しました。Fir for 55では、エネルギー、気候、輸送、課税等の広範囲な政策分野が対象とされています。この中では、2030年のEUのエネルギーミックスにおける再エネの導入目標を、2018年に発表された32%から40%まで引き上げることや、エネルギー課税指令の改正による船舶輸送と航空機への免税措置の廃止等、温室効果ガスの排出削減に向けた施策が打ち出されました。
ロシアによるウクライナ侵略が始まった直後の2022年3月には、エネルギーの価格高騰及び需給ひっ迫への短期的な対応と、ロシア産エネルギーからの脱却を2本柱として掲げた「REPowerEU計画8」を発表しました。Fit for 55で掲げていた投資に加え、2027年までに2,100億ユーロの追加投資を掲げる新たな計画です。
REPowerEU計画には再エネへの移行の加速が掲げられています。2030年の再エネの導入目標を、Fit for 55で掲げた40%から45%に引き上げることとし、具体策として太陽光発電を強化するEU太陽光戦略を発表しました。その中では、現在の発電容量が約200GWとなっている太陽光について、2025年までに発電容量を320GW以上に増やし、さらに2030年までには約600GWへと増やすことを目指しています。また、REPowerEU計画では水素や電化についても言及しています。水素については、2030年までの域内生産目標を年間約1,000万トンまで引き上げるとともに、同量を域外からも輸入する計画を立てています。2030年までにはEU水素市場を開設することも掲げており、再エネ由来の水素のコスト競争力向上を目指しています。電化についてはREPowerEU計画の発表から5年間で累計1,000万台のヒートポンプを導入することを目標として掲げ、産業界の電化促進を目指しています。
また2023年2月には、持続可能なEU経済の実現に向けた成長戦略である「欧州グリーン・ディール」の実現に向けた構想である「グリーン・ディール産業計画9」を発表しました。EUをカーボンニュートラルの達成に必要なクリーンテックや産業の技術革新の中心地とすることを目指した新たな計画です。この計画では、「規制環境の改善」、「資金調達の支援」、「人材開発」、「貿易の促進」を4つの柱としており、例えば、規制環境の改善については「ネットゼロ産業法案」を発表しました。このネットゼロ産業法案では、風力やヒートポンプ、太陽光、水素等のカーボンニュートラル達成に必要なクリーンテックに関する2030年までの目標を設定した上で、その製造拠点の整備に必要な許可手続の簡略化と迅速化を図っています。また、同法案では、特定の太陽光発電や風力発電等を「戦略的ネットゼロ技術」とし、2030年までにEU域内での自給率を40%とする目標が示されています。
(3)英国
英国政府の「ネットゼロ戦略」を実現するために、2021年に260億ポンド(1ポンド162円換算で約4兆円規模)の設備投資を行うことを掲げた10英国では、2050年のカーボンニュートラルの実現という長期的な目標を掲げつつも、ロシアへのエネルギー依存度を下げる観点から、クリーンな国産エネルギーへの転換が着目されました。ロシアによるウクライナ侵略による世界的なエネルギーの価格高騰に対応し、クリーンで安価なエネルギーへの転換を図るため、2022年4月、これまでの計画よりもさらに脱炭素社会への移行を加速する「エネルギー安全保障戦略11」を発表しました。
この戦略における主な施策として、2035年までに太陽光を最大70GW(現状は約14GW)、2030年までに洋上風力を最大50GW(現状は約13GW)まで増加させることが挙げられており、クリーンな国産エネルギーである再エネを拡大させる方針が見られます。また、原子力については2030年までに最大8基の原子炉新設を掲げており、2050年までに最大24GW(現状は約8GW)の出力を整備し、電力需要の最大25%(現状は15%)を賄うことを目指しています。水素については2030年までに低炭素水素の生産能力を10GWまで増加させることを掲げています。このエネルギー安全保障戦略では、石油・ガスについても方針が挙げられています。英国内でガスを生産することは海外から輸入する場合に比べて温室効果ガスの排出量が少ないとし、新規の北海石油・ガスプロジェクトの認可プロセスを開始する予定です。
また、エネルギー安全保障戦略以外にも、例えば「EVインフラ戦略」等の脱炭素に向けた計画も発表されています。EVインフラ戦略では、2030年までにEVの公共充電設備の設置台数を現在の約3万台から30万台に増やす計画を示しており、EVの充電がガソリン車やディーゼル車の給油よりも簡単で安価になることを目指しています。
2022年11月に行われたCOP27では、電力、陸上輸送、鉄鋼、水素、農業等の分野における新たなグリーンテクノロジーの開発に注力する方針も打ち出しています。こうした新たな開発を促進すべく、特に途上国のエネルギー集約型産業のグリーン化に向けて、6,500万ポンドを超える投資を行うと発表しています。英国が、脱炭素社会の実現を目指す国際市場において、存在感を示す一例となっています。
(4)ドイツ
ドイツでは、他の多くの国がカーボンニュートラルの実現を掲げる2050年よりも5年前倒しした2045年のカーボンニュートラル達成を掲げています。2020年から2021年にかけて実施された約1,300億ユーロ規模の経済刺激策においては、うち500億ユーロが気候変動に対応するモビリティとデジタル化に充てられ、EV購入補助金の倍増、EVの車両税の減税期間の延長等が行われました。
2022年4月には、エネルギー政策関連法の改正案をまとめた「イースターパッケージ12」が閣議決定されました。このパッケージには再エネの拡大に関する複数の法律が含まれており、代表的なものとしては再生可能エネルギー法(EEG)、洋上風力エネルギー法等があります。EEGでは、2030年までに電力消費量の80%を再エネ由来の電力とし、2035年には国内の電力供給をほぼ再エネで賄うという方針を掲げています。
再エネに限らず、ドイツでは水素も脱炭素社会の実現に向けて重要な役割を担うと位置づけています。2020年には国家水素戦略を公表し、90億ユーロの投資を行うことを発表しています。今後、2030年までに5GW、2040年までに10GWの水素製造能力を国内で保持することを目標にしています。一方で、ドイツは国内の生産能力だけでは国内の水素需要(鉄鋼工場、化学施設、輸送等)を満たすに不十分としており、国外からの水素の輸入を強化する動きも見せています。2022年8月には、将来的にグリーン水素の生産が有望とされているカナダと、グリーン水素市場の拡大を目指した協定を締結しました。また、同年12月には、EU域外でのグリーン水素の生産と輸入を推し進めるための「H2グローバル13」プロジェクトの始動を発表しました。アフリカを始め、EUや欧州自由貿易連合(EFTA)以外のグリーン水素生産に適した国・地域との連携を強めています。
また、2022年12月に、気候変動対策を推進するための新たな枠組みとして「気候クラブ」が設立されましたが、これはドイツが2021年から提唱し、設立を促進してきたものです。
前章の第1節でも記載したとおり、ドイツでは今回のロシアのウクライナ侵略を受けて、ロシア産エネルギーに代わる足元のエネルギーを確保するために、停止中の石炭火力発電所の再稼働や、廃止を予定していた原子力発電所の稼働期間の延長等、短期的には、これまで進めてきたエネルギー政策の見直しを余儀なくされました。しかし、同時にイースターパッケージやH2グローバル、気候クラブといった中長期的な脱炭素社会の実現に向けた動きも引き続き見られています。
(5)フランス
フランスは、2022年2月に発表したエネルギー政策に基づき、2050年のカーボンニュートラル実現を目指しています。化石エネルギーからの脱却手段として、原子力と再エネの2本柱を掲げています。
フランスは過去からエネルギーの多くを原子力で賄ってきた国として知られていますが、ボルヌ首相が2022年7月に行われた施政方針演説にて、原子力を推進する方針を確認し、再エネの普及拡大と同時に、次世代原子炉の建設と未来の原子炉開発に投資すると述べました。また、エネルギー安全保障の確保と脱炭素化を目指して政府のエネルギー産業への関与を強めることを目的に掲げ、具体策として、フランス最大の電力会社EDFの完全国有化を実施しました。
再エネについては、2023年3月に再エネ生産加速法が施行されました。2050年までに、太陽光発電の発電容量を100GW超に増やすとともに、洋上風力と陸上風力の発電容量をそれぞれ40GWまで増やす目標の達成を目指し、再エネ生産計画の策定プロセスの整備、行政手続の簡素化、既に開発済の土地の活用拡大、再エネ生産から得る利益の再分配強化の4つを柱としています。
また、フランスは水素分野の取組にも積極的です。2020年には国家水素戦略14を発表し、国内における水素関連素材の開発・生産を支援しつつ、エネルギー集約型産業においてグリーン水素を使った脱炭素化を進めてきました。2022年には水素分野における欧州共通利益に適合する重要プロジェクト(IPCEI)に承認された水素関連プロジェクト10件に、21億ユーロの補助金を出すことをボルヌ首相が公表し、グリーン水素の世界的リーダーを目指す姿勢を明らかにしました。
(6)インド
インドは2070年までのカーボンニュートラル達成を目指しています。2021年のCOP26におけるカーボンニュートラル宣言以降、気候変動対策に関する政策を打ち出してきました。
2021年8月には、2030年までにグリーン水素の年間生産量を500万トンまで増やすことを目標に掲げた「国家水素ミッション」が策定され、翌年となる2022年には、その具体的な計画である「グリーン水素・アンモニア政策」を発表しています。その中では、2025年6月までに開始されたプロジェクトを対象に、グリーン水素・アンモニアメーカーは25年間にわたって送電料金の支払が免除される等、グリーン水素・アンモニアの製造を推進していく内容が提示されています。
2022年8月には、COP26気候変動会議におけるグラスゴー気候協定を受けて、2015年にNDCとして提出していた目標(2030年のGDP当たりの温室効果ガスの排出量を2005年比で33〜35%削減)を見直す形で、2030年までにGDP当たりの温室効果ガスの排出量を2005年比で45%削減し、非化石エネルギーによる電力調達を50%程度とすることを含む、新たな気候変動対策を閣議決定しています。
(7)韓国
韓国も2050年のカーボンニュートラル達成を目指しています。そのための戦略として、2022年10月には「カーボンニュートラル・グリーン成長推進戦略」、「カーボンニュートラル・グリーン成長技術革新戦略」が発表されました。前者では、原子力・再エネのバランスの確保や、エネルギーミックスの再構築等に関する戦略が示され、後者では、技術開発に関する基本的方向性が示されています。技術開発の対象としては、超高効率太陽電池システムや小型モジュール炉(SMR)、水素還元製鉄の製造技術等が含まれています。
原子力については2022年5月の政権交代に伴い、前政権が進めてきた脱原子力政策が転換されることとなっています。政権交代後の同年7月に国務会議で議決された「新政権のエネルギー政策方向」においては、既存の原子力発電所の継続運転に必要な手続を迅速に促進するとともに、開発が中断されていた新ハンウル3・4号機の建設再開、原子力の輸出促進、独自の小型モジュール炉(SMR)の開発促進を行っていく方針が発表されました。
また2023年1月には、実現可能でバランスの取れた電源ミックスや、原子力の活用・適正水準の再エネを基本方針として掲げる「第10次電力需給基本計画15」が発表されています。エネルギーの安定供給を最優先に、経済性、環境適応、安全性等を総合的に考慮した計画となっており、2036年までに石炭火力を減少させる一方で、原子力、LNG火力及び再エネを拡大させる方針が示されています。
(8)その他
その他の国でも、脱炭素社会を目指した動きは活発化しています。例えば水素社会の実現においては、2060年のカーボンニュートラル実現を目指す中国が、2022年3月に「水素エネルギー産業発展中長期規画16」を発表しており、その中では2025年までに水素燃料電池自動車の保有台数を5万台、グリーン水素の製造を年間10〜20万トンとすること等を掲げました。
原子力については2023年1月にスウェーデン政府が、原子力に関する改正法案を提案し、原子力発電の建設に関する規制を撤廃しようとしています。具体的には、既存の原子力発電所がある場所以外の場所での原子炉の建設を禁止する環境法の規定や、運転中の原子炉の数を10基までに制限する規定を削除することを提案しました。本改正に関してスウェーデン政府は、電化や脱炭素燃料への移行において、さらなるクリーンな電力、あらゆる種類の非化石エネルギーが必要だと述べており、さらにより多くの場所により多くの原子力発電所を建設することを可能にしたいという意向も示されています。
- 1
- 産業革命以前に比べて、世界の平均気温の上昇を2℃以下に、できる限り1.5℃に抑えるという目標。
- 2
- GFANZ:Glasgow Financial Alliance for Net Zeroのことで、ネットゼロ金融イニシアティブを取りまとめ、ネットゼロ移行への加速目指す、民間主導のイニシアティブ。
- 3
- NZBA:Net Zero Banking Allianceのことで、2050年までの投融資ポートフォリオのカーボンニュートラルにコミットする銀行によるイニシアティブ。
- 4
- GFANZ 「Net-zero Transition Plan」(2022年6月公表)
- 5
- NZBA 「NZBA Transition Finance Guide」(2022年10月公表)
- 6
- U.S. Department of Energy「Industrial Decarbonization Roadmap」(2022年9月発表)
- 7
- European Commission「The European Green Deal Investment Plan」(2020年1月14日発表)
- 8
- European Commission「REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy」(2022年3月8日発表)
- 9
- European Commission「The Green Deal Industrial Plan」(2020年2月1日発表)
- 10
- 英国政府「BEIS in the Spending Review 2021」(2021年10月28日発表)
- 11
- 英国政府「British energy security strategy」(2022年4月7日発表)
- 12
- ドイツ政府「Easter Package」(2022年4月6日閣議決定)
- 13
- ドイツ連邦経済・気候保護省「H2Global」(2022年12月公表)
- 14
- フランス政府「Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogéne décarboné en France」(2020年9月公表)
- 15
- 韓国産業通商資源部が発表した2022年から2036年までの電力の基本的な方向性、長期の需給見通し、発電ならびに送配電設備計画、需要管理及び分散型電源などの内容を含む計画。
- 16
- 中国・国家発展改革委員会が2022年3月に発表した、2021年から2035年の同国水素エネルギー産業に関する発展戦略計画。